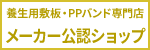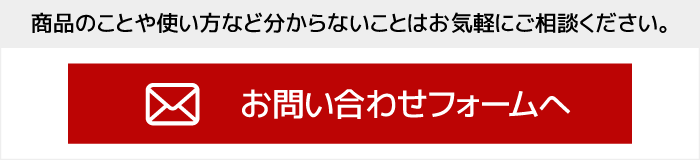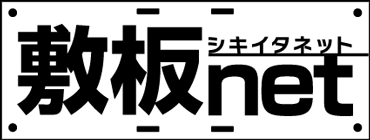バタ角とは?資材仮置用枕木や、りん木との違いはあるのか?
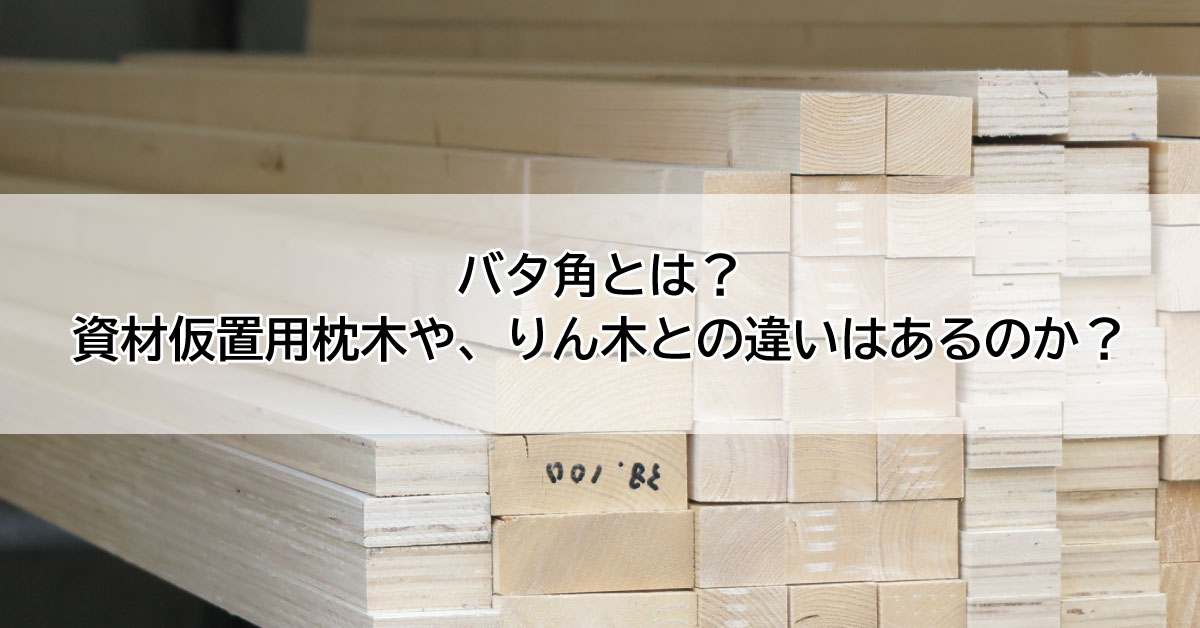
- りん木・角材
物流現場で木材や荷物の仮置に使われるりん木。これは、単にバタ角と呼ばれる材木が用いられることもあります。
ですが、バタ角とりん木には厳密には様々な違いがあります。まず、バタ角の素材は木材だけではないこと。バタ丸と呼ばれるパイプ状の資材もあること。物流現場だけでなく、建築現場でも幅広く利用されていることなどです。
では、物流現場を中心に、どのようなバタ角材が用いられているのか、素材に違うメリットデメリット、今後の課題などについて解説していきましょう。
バタ角とは
建築工事のコンクリート打設のときに、型枠仮補強などに使われます。このときのバタ角は、10センチ程度の木材であることが多いですね。
建設現場で使われる場合は、10センチ角程度のパイプがよく用いられています。ちなみに建設現場で作業するための足場資材として、単管パイプが使われるがこちらは「バタ丸」と呼ばれている。バタ丸の場合は厚み2.4mm、連結の際にボンジョイントという継ぎ手の金具を用います。
ボンジョイントは、足場のように人が乗るシーンでの使用は禁止されているので、注意しなくてはいけません。結合部が非常に弱く、人体程度の荷重にも耐えられないからです。
他にも、重量物を仮置するときに敷くダンネージ、枕木としても利用されることがあります。ダンネージに木材か使われている場合、リン木やばん木などと呼ばれることもあります。
参考 厚生労働省Webサイト:労働者の安全と健康の確保:職場における安全対策「単管足場に「ボンジョイント」を使用しないで下さい!!」
参考 大和鋼管工業株式会社ブログ:素朴な疑問。バタ丸/バタ角のバタってなに? (・・?

バタ角、バタ丸の「バタ」とは??
一般的に物流資材の仮置として使われる場合のりん木、バタ角。このバタの意味はなんでしょうか。
俗に「ばたっと置くからバタ角」などと言われています。たんにバタとよばれることも。
より専門的には「端太」と書いてバタ、と読むという説が指示されてきます。「端に置いてつかう太い木材だから」という由来であると考えられているからです。
バタ角の素材
建設現場では鋼鉄製のものが好まれ、物流資材仮置のシーンでは、木材が一般的です。
その他にも、アルミ製のもの、ハイテン仕様のものなどが種類は様々。建設現場で用いられるアルミ製のバタ角は、軽量であり、組み立て、撤去の作業効率がアップされるというメリットがあります。
また湿気にも大変強く、耐久性も高い。さらにリサイクル率も高いので経済的という特徴も持っているハイクオリティな素材なのです。
その一方で、やはり鋼鉄製バタ角に比べると強度で劣り、溶接がしづらく、コストも若干高めというデメリットがあるのは無視できませんね。
ハイテンバタ角とは、高張力鋼板といって、引っ張るという方向に力がかかったときに強度を発揮する鋼材で作られたバタ角です。
同じ大きさの鋼鉄製バタ角と比べて、厚みが薄く重さも30%カット出来ています。安全強度は問題ないので、運搬、移動の負担を大幅に改善した素材です。

りん木、ダンネージとして木材を使うデメリット
材木の仮置きには、木製の角材がよく使用されます。しかし、木材だとどうしても乾燥して割れてしまうリスクがあるのです。これを木割れと言います。
木の細胞は常に、膨張、収縮繰り返す自律運動を行っています。この過程で急激に乾燥が進むと、木割れが起こるのです。
角材は板材に対して厚みを持っているので、どうしても木割れを起こしやすく、一度割れ目が入ってしまうと強度が落ちて折れやすくなるのは避けられません。
参考 木の博物館 木力館:7.木の割れについて

木割れを防ぐには
木の呼吸を止めることが重要です。ウレタン塗装などで木の表面をコーティング、呼吸出来なくさせる、または人工的に強制乾燥させるなどの方法が取られています。あるいは、高温の窯の中に材木を入れて一気に水分を抜くこともあります。。
りん木としても利用されるバタ角と課題
角材は建築現場、物流現場に欠かせない資材だが、その中でもりん木として利用されるものを特にバタ角ということもあります。つまり、物流現場において両者はほぼ同じものとして使われているのです。
従来のバタ角は、木材であることから耐久性、耐水性に限界があることが課題でした。
そこで2021年現在、再生プラスチックやウッドプラスチックで合成された樹脂製のバタ角の開発も進められています。
最大の特徴は水分、湿気に強いことで、強度も確保されているので繰り返しの利用に耐えられる。
そして木材とちがい、全く同じ形に整形することが可能で量産できるので、供給の問題を解決できるかもしれません。また、不動沈下によって輸送途中の荷崩れが起こるのも防げるので、生産拡大による普及が待たれます。