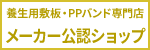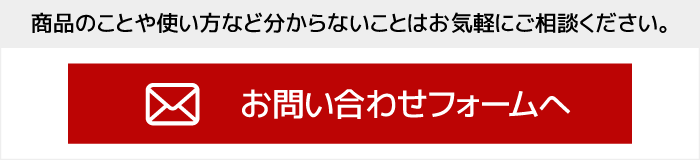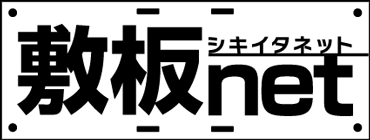梱包とは?梱包の種類をご紹介!
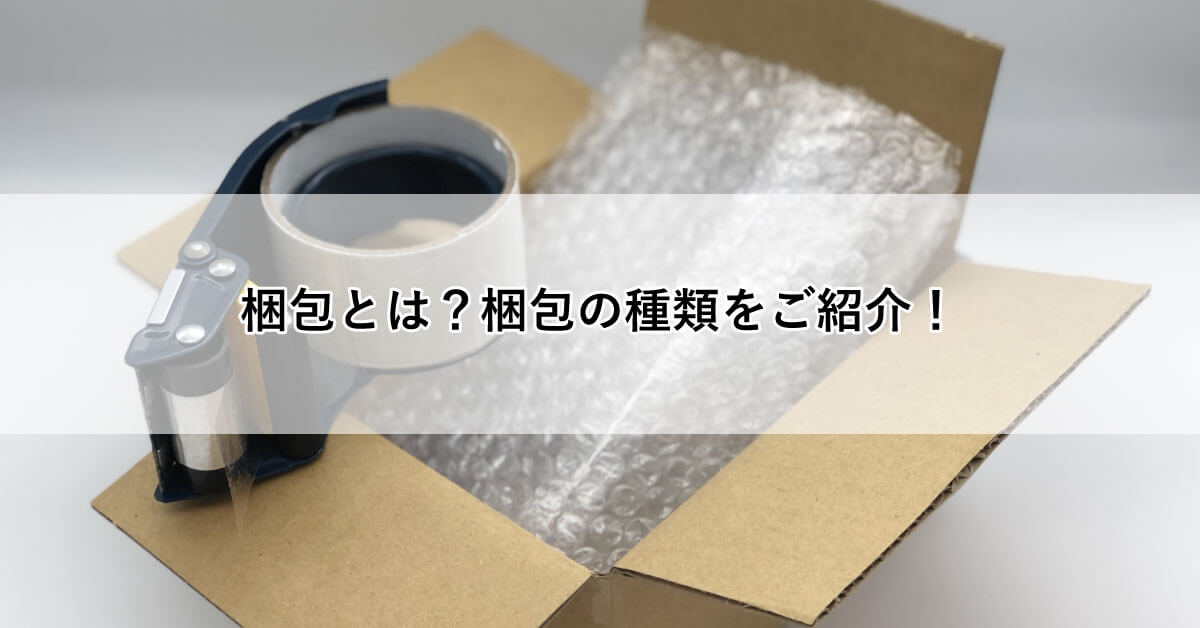
- 緩衝材
「梱包」って何?「包装」との違い
今回ご紹介する「梱包」に似た言葉で「包装」がありますが、この2つの違いについてまずは調べてみました。
こんぽう【梱包】 覆いや縄などをかけて荷造りすること。また、その荷造りしたもの。
商品や荷物を段ボール箱などに入れて、荷物をまとめる作業が梱包にあたります。輸送する際に荷物の破損を防いだり、荷物をひとまとめにすることで運びやすくすることができます。
ほうそう【包装】 うわづつみをかけること。また、うわづつみ
包装は、包装紙で商品を包んだり、リボンをかけるなど装飾の意味合いを持ちます。プレゼントを贈るときに、デパートなどでラッピングをしてもらいますよね。商品を魅力的に「包み装う」こととして使われています。
ちなみに、日本産業規格(JIS)では、以下のように「包装」が定められています。
「物品の輸送、保管、取引、使用などにあたって、その価値および状態を維持するために適切な材料、容器などの物品を収納すること及びそれらを施す技術、または施した状態。これを個装、内装および外装の3種類に大別する。パッケージともいう。
参考:日本工業規格ー包装貨物
個装・・・物品個々の包装で、物品の商品価値を高めるため、または物品個々を保護するために適切な材料・容器などを物品に施す技術、または施した状態。
内装・・・包装貨物の内部の包装で、物品に対する水、湿気、光、熱、衝撃などを考慮して、適切な材料・容器などを物品に施す技術、または施した状態。
外装・・・包装貨物の外部の包装で、物品または包装物品を箱、袋、樽、缶などの容器などに入れ、もしくは無包装のまま結束し、記号、荷印などを施す技術、または施した状態。パッキングともいう。
一般的に、①個装が「包装」に、②内装③外装が「梱包」に使用されることが多いようです。
身近になった「梱包」作業
八百屋さんに肉屋さん、魚屋さんなど、商品ごとに取り扱っているお店があり、買い物かごや豆腐などは入れる容器を持参し、各商店で対面販売が主流の時代がありました。一時的な保存や近い場所への持ち運びなどのために「包む」ことがされていましたが、持ち運びが容易で保存も利く瓶詰めや缶詰、インスタントやレトルト食品などの普及、スーパーマーケットの登場により、消費者がほしい商品を選び、かごに入れレジへ持って行くセルフサービスへと変わったことで、あらゆる商品が包装されるようになりました。食品など私たちが日常的に手にする商品は個包装されている物が多いですが、スーパーなどには段ボールなどにまとめて梱包、配送されます。家電等にいたっては、1台ずつ梱包されていますよね。商品の破損を防ぎ、尚かつ積み込みやすく、効率よく輸送できるようにするという目的で「梱包」が身近になってきました。
梱包の種類
「梱包」は「段ボール箱に荷物を詰める」というイメージですが、段ボールを使用する以外の梱包方法があります。ここでは梱包の種類について、ご紹介したいと思います。
段ボール梱包
みなさんご存じの段ボールで梱包する方法です。段ボールは緩衝に強く、軽くて強度があるので持ち運びが便利です。一般的な段ボールだけではなく、原紙を貼り合わせた強化段ボールは、重量のあるものでも梱包できます。中仕切りなどを段ボールにすることで、さらなる緩衝や固定も可能です。古紙としてのリサイクル率も95%以上で、再利用できるのが特徴です。水に弱いなどデメリットもありますが、撥水や防水・防湿などの機能性段ボールも登場しており、現在では輸送梱包の大半を占めています。

真空梱包
酸素を取り除き真空状態で梱包する方法です。食品は鮮度を守ったり、酸化や劣化を防ぐなどの目的で使用されます。また、輸送中に気温変化や結露で錆びる恐れのある金属製品や電子部品などの工業製品でも多く使用されるようになりました。
木製梱包
木箱や木枠などで梱包する方法です。重量のある荷物や取り扱いや配送が難しい異形貨物などを輸送する際に、外部からの力に対して内容物を保護し、荷扱いを容易にする目的で使用されます。古くから使われている木製梱包材ですが、現在では有害な動植物の侵入経路となる場合があり、国外輸送など植物検疫が適用されますので、注意が必要です。

スチール梱包
スチール製の容器で商品を梱包する方法です。よく見かけるのは、お中元・お歳暮などに送られるお煎餅の容器ですね。
木製梱包の検疫規制が厳しくなっているため、木材と同等の強度があり、梱包・開梱が容易なスチール梱包が増えてきています。木製梱包などに比べると、コストが高くなる点が難点です。

今回は「梱包」についてざっくりとご紹介しました。
次回は、梱包資材について、お伝えしたいと思います。